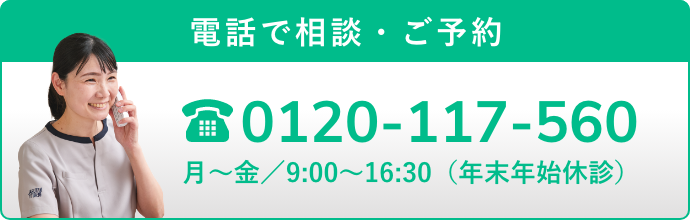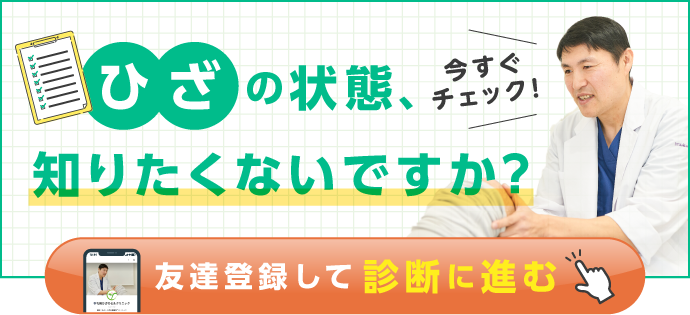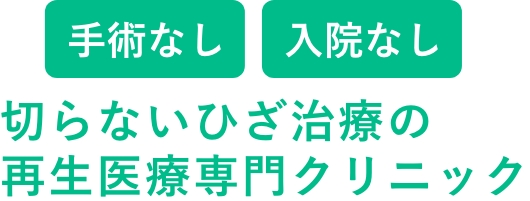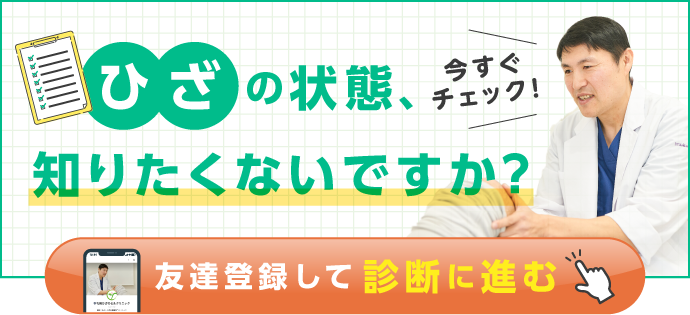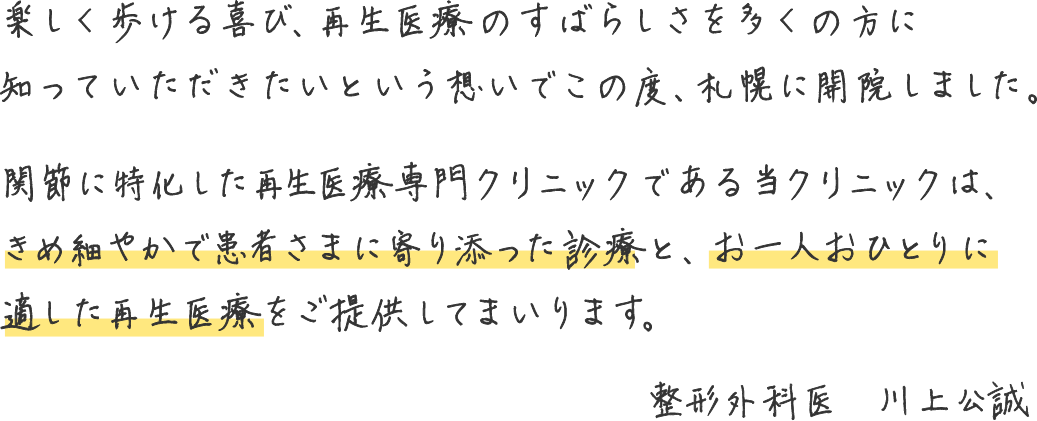
コラム COLUMN
スポーツ外傷膝 運動後のひざ痛はなぜ起こる?放置するリスクと対策

「運動をした後に、なんとなくひざが痛む…」「しばらく休めば治るだろう」と思っていませんか?
実はそのひざの痛み、放っておくと慢性化したり、関節の変形につながる恐れがあります。
本記事では、運動後にひざが痛くなる原因と、放置するリスク、そして対策方法について、整形外科専門医の立場からわかりやすく解説します。
この記事の内容
ひざは運動のたびに大きな負担を受けている
ひざ関節は、歩行・階段の上り下り・スポーツなど、あらゆる動作に関与しています。
体重の3〜5倍もの負荷がかかることもあり、特に運動後には筋肉や腱、靭帯、関節内の軟骨や半月板に小さなダメージが生じることがあります。
正常な場合、ダメージは自然に修復され、痛みも一時的で済みます。しかし、疲労の蓄積や関節の炎症、構造的な異常がある場合には、痛みが長引くことがあります。
運動後にひざが痛くなる主な原因
以下のようなケースが、運動後のひざ痛の原因としてよく見られます。
1. オーバーユース(使いすぎ)
運動量が急激に増えたときや、無理なフォームでトレーニングを続けたときに起こります。
特にジャンプやランニング、スクワットなど反復動作の多いスポーツでは、膝蓋腱炎(ジャンパー膝)や腸脛靭帯炎(ランナー膝)が見られます。
2. 筋力不足・柔軟性低下
太ももの筋肉(大腿四頭筋やハムストリングス)の柔軟性や筋力が低下していると、ひざへの負担が増します。
加齢による筋力低下が背景にあることも多く、中高年でのひざ痛につながります。
3. 軟骨や半月板の損傷
すでに軽度の変形性ひざ関節症が進行していたり、半月板がすり減っていたりすると、運動後に痛みが強くなります。
「朝は痛くないけど、夕方にかけて痛くなる」という方は、このタイプが多い傾向です。
放置するとどうなる?進行するリスク
「一晩寝たらよくなった」「湿布でごまかしている」という対応は、症状を見逃す原因となります。
運動後のひざ痛を放っておくことで起こりうるリスクは以下の通りです。
- 軟骨のすり減りが進行し、変形性膝関節症に移行する
- 炎症が慢性化し、慢性滑膜炎に
- 痛みのために運動を避け、筋力低下や体重増加の悪循環に
- スポーツパフォーマンスの低下や、日常動作での支障
早期に原因を見極め、適切な対策をとることが大切です。
ひざ痛を防ぐためにできる対策
1. アイシングと休息
運動後に痛みや熱感がある場合は、まず冷やして炎症を抑えることが大切です。
目安は15〜20分、氷嚢や冷却シートを使いましょう。
2. ストレッチと筋トレ
日常的にストレッチを取り入れ、太ももやお尻の筋肉を柔らかく保ちましょう。
特に大腿四頭筋・ハムストリングス・中臀筋のトレーニングが、ひざへの負担軽減に効果的です。
3. 正しいフォームでの運動
フォームが崩れると、ひざに偏った負荷がかかります。
自己流ではなく、専門家の指導を受けることも大切です。
4. 定期的な医療チェック
ひざに違和感や痛みを感じたら、整形外科や関節専門クリニックでの検査をおすすめします。
レントゲンやMRIで異常を早期に見つけることで、重症化を防ぐことができます。
再生医療という選択肢も
もし「軟骨のすり減りが原因」と診断された場合、再生医療という手術に頼らない治療法もあります。
当院では、自分の脂肪や血液を使った幹細胞治療・PRP治療を提供しており、関節の修復を促すことが可能です。
早期の段階で取り組めば、運動を長く続けたい方の大きな味方になります。
まとめ
運動後のひざ痛は、体のSOSサインかもしれません。
一時的な痛みだからと軽視せず、原因を正しく理解し、早めの対策を行うことが大切です。
ひざの健康を守ることで、これからも楽しく体を動かし続けられる毎日を手に入れましょう。
札幌ひざのセルクリニックでは、患者様の症状に合わせた適切な診断と治療計画のご提案をしております。ひざだけでなく、肩、股関節等の関節、また長引く腰痛などの慢性疼痛の治療も行っております。西18丁目駅徒歩2分、札幌医大目の前にありますので、お気軽に御相談下さい。
院長 川上公誠
(プロフィール)
監修 川上 公誠(整形外科専門医)
札幌ひざのセルクリニック院長
岐阜大学医学部卒業。母が人工関節手術で痛みから解放された経験をきっかけに整形外科医を志し、これまでに人工関節置換術を含む手術を5,000件以上手がけてきました。手術が難しい高齢者や合併症のある方にも寄り添える治療を模索する中で再生医療と出会い、その効果に確信を得て、2024年に「札幌ひざのセルクリニック」を開院。注射のみで改善が期待できるこの先進的な治療を、北海道中に届けたいという想いで、関節に特化した再生医療を提供しています。
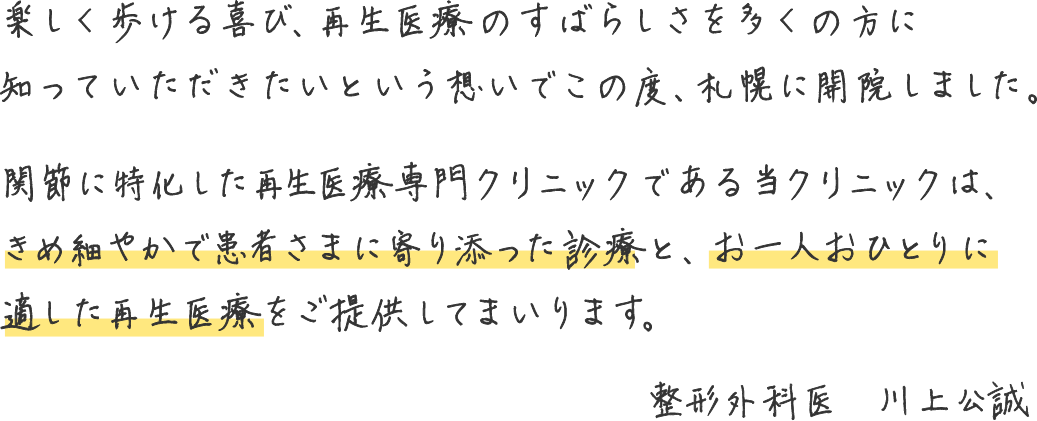

各種ご相談やご予約はこちら
- ひざの痛みに関する相談
- セカンドオピニオンの相談
- 再生医療に関する相談
- MRI検査のご予約