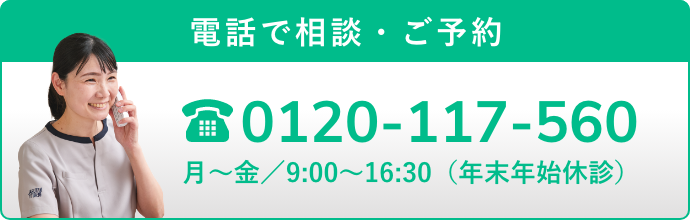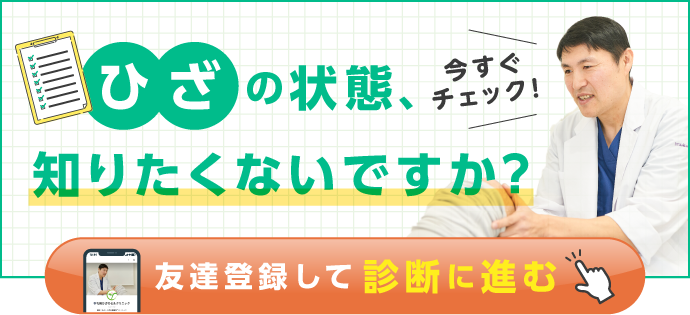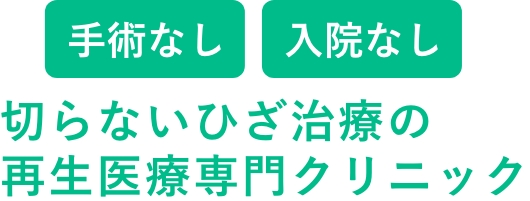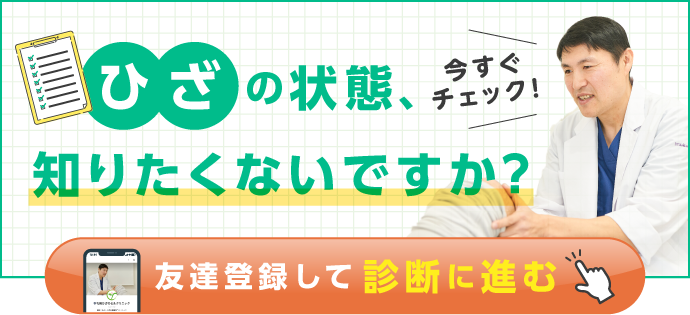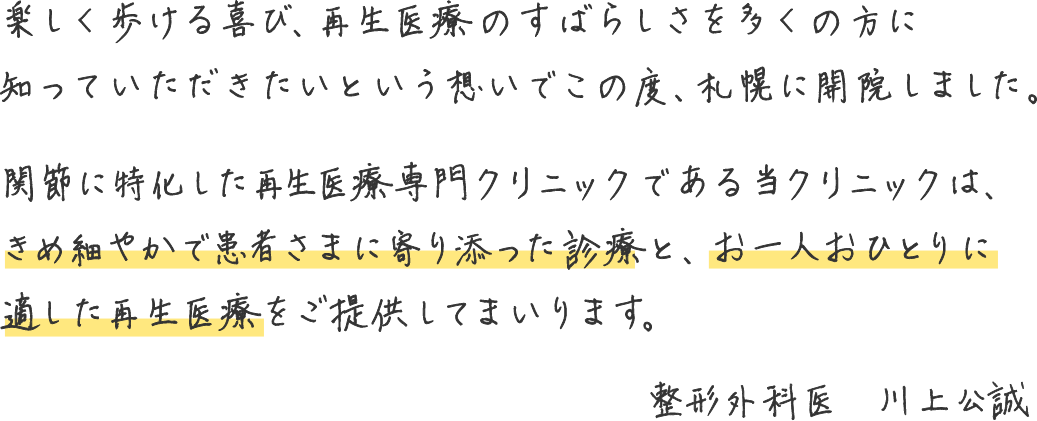
コラム COLUMN
再生医療 なぜ保険診療の医師は再生医療を勧めないのか?理由と背景を解説
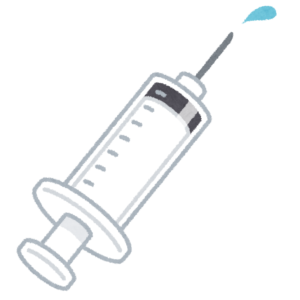
近年、関節の痛みや変形性関節症に対する治療法として「再生医療」が注目されています。しかし、保険診療を行う一般の医師が再生医療を勧めることはあまりありません。その理由として、高額な治療費が挙げられますが、それ以上に「再生医療に関する知識が乏しい」ことが根底にあると考えられます。本記事では、その背景について詳しく解説します。
この記事の内容
保険診療と自由診療の違い
医療には「保険診療」と「自由診療」の2種類があります。
- 保険診療:国の健康保険制度に基づき、患者の自己負担額が3割(高齢者は1割~2割)となる。診療内容は保険適用内に限られる。
- 自由診療:保険が適用されない治療であり、患者が全額自己負担する。再生医療は基本的にこちらに分類される。
保険診療の医師は、基本的に国が定めた治療のみを提供し、それ以外の治療法にはあまり関与しません。そのため、自由診療である再生医療について詳しく学ぶ機会が少ないのが実情です。
保険診療の医師が再生医療を勧めない理由
① 再生医療に関する知識が少ない
多くの保険診療の医師は、大学や病院で保険診療に関する教育を受け、日常診療でも保険適用の治療を提供しています。再生医療は比較的新しい分野であり、保険診療では取り扱わないため、医師が学ぶ機会が限られています。その結果、患者に適切な説明ができず、「まだ確立されていない」「効果がわからない」といった理由で勧めないことが多いのです。
② 再生医療は保険適用外で高額
再生医療は自由診療であり、費用が高額になりやすいのも一因です。保険診療の医師は、患者の経済的負担を考慮し、自由診療の治療を勧めにくい傾向があります。特に、公立病院や大病院では「コストのかかる治療は避ける」という風潮があり、結果として再生医療が選択肢に入らないことが多いのです。
③ 既存の治療法を優先する傾向
保険診療の現場では、
- ヒアルロン酸注射
- 鎮痛薬の処方
- 理学療法
- 人工関節手術 といった既存の治療法が標準的に提供されます。再生医療は新しい治療法であるため、長年の臨床実績がある従来の治療が優先されがちです。
④ 病院の方針やガイドラインに従う必要がある
大病院や保険診療を主体とするクリニックでは、医師個人の判断で自由診療の治療を勧めることが難しい場合があります。病院の方針やガイドラインに従う必要があるため、再生医療が選択肢として出てこないこともあります。
再生医療の有効性と安全性
再生医療は比較的新しい治療法ですが、国内外で多くの研究が行われ、効果が示されています。
- 幹細胞治療:変形性膝関節症の進行を抑え、痛みを軽減することが報告されています。
- PRP療法:スポーツ選手の治療にも活用され、関節の損傷修復を促す効果が認められています。
さらに、日本では「再生医療等安全性確保法」に基づき、安全性が確保された医療機関のみが提供できるため、適切な施設で受ければ安心です。
患者自身が選択する時代へ
保険診療の医師が再生医療を勧めない背景には、知識不足や病院の方針などが関係しています。しかし、情報が広がる現在、患者自身が治療の選択肢を知り、最適な方法を選ぶことが重要になっています。
① 医師に積極的に質問する
保険診療の医師が再生医療について詳しくない場合でも、気になることがあれば積極的に質問しましょう。また、再生医療の専門クリニックで相談することも有効です。
② 信頼できる情報を集める
再生医療については、信頼できる医療機関や公的機関の情報を参考にし、適切な知識を得ることが大切です。
③ 早期の治療を考える
変形性関節症などの慢性疾患は進行するため、早期に適切な治療を受けることが重要です。再生医療は病気の進行を抑える可能性があるため、手遅れになる前に検討する価値があります。
まとめ
保険診療の医師が再生医療を勧めない理由には、
- 再生医療に関する知識が不足している
- 保険適用外で高額である
- 既存の治療法が優先される
- 病院の方針やガイドラインの影響 などが挙げられます。
しかし、再生医療は科学的な研究に基づいた治療であり、適切な医療機関で受けることで安全性も確保されています。最適な治療を選ぶために、患者自身が積極的に情報を収集し、専門医に相談することが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q1. なぜ保険診療の医師は再生医療を勧めないのですか?
A. 再生医療は保険適用外で高額なうえ、多くの保険診療医は知識や経験が乏しく、病院の方針やガイドラインに縛られるためです。
Q2. 再生医療は本当に効果があるのでしょうか?
A. 幹細胞治療やPRP療法は研究により一定の効果が報告されています。専門の医療機関で安全性を確保したうえで提供されています。
Q3. 再生医療を受けたい場合はどうすればいいですか?
A. 再生医療を専門に扱うクリニックに相談するのがおすすめです。信頼できる情報を集め、早期の治療を検討することが重要です。
札幌ひざのセルクリニックでは、患者様の症状に合わせた適切な診断と治療計画のご提案をしております。ひざだけでなく、肩、股関節等の関節、また長引く腰痛などの慢性疼痛の治療も行っております。西18丁目駅徒歩2分、札幌医大目の前にありますので、お気軽に御相談下さい。
院長 川上公誠
(プロフィール)
監修 川上 公誠(整形外科専門医)
札幌ひざのセルクリニック院長
岐阜大学医学部卒業。母が人工関節手術で痛みから解放された経験をきっかけに整形外科医を志し、これまでに人工関節置換術を含む手術を5,000件以上手がけてきました。手術が難しい高齢者や合併症のある方にも寄り添える治療を模索する中で再生医療と出会い、その効果に確信を得て、2024年に「札幌ひざのセルクリニック」を開院。注射のみで改善が期待できるこの先進的な治療を、北海道中に届けたいという想いで、関節に特化した再生医療を提供しています。
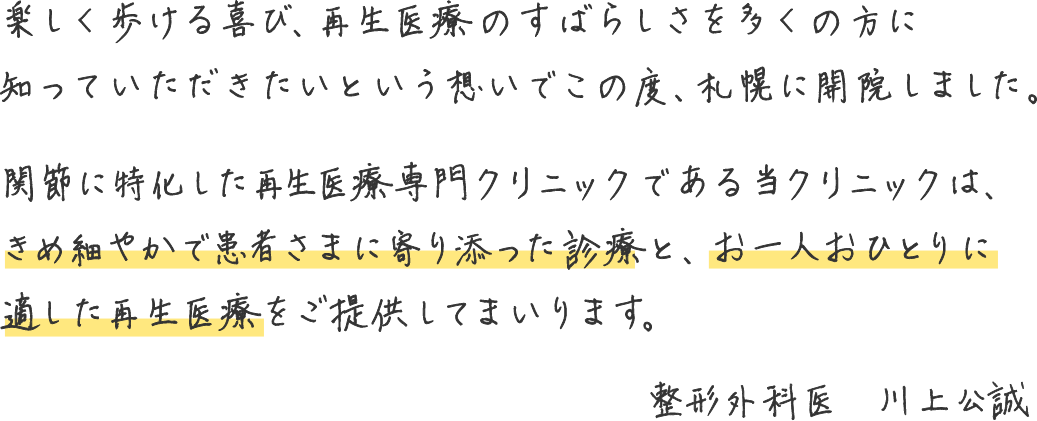

各種ご相談やご予約はこちら
- ひざの痛みに関する相談
- セカンドオピニオンの相談
- 再生医療に関する相談
- MRI検査のご予約